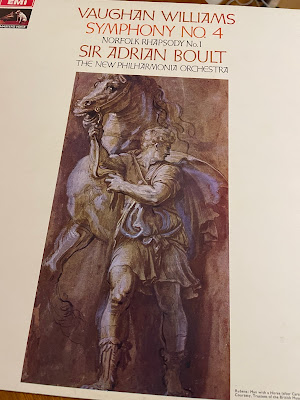5月も今日を入れて残すところ2日。早々と梅雨入りするかと思われたが晴れの日も多く、ジメジメ・ムシムシもせず、過ごしやすい日が続いている。
ブログはアジサイをイメージしたものに変えてみた。
今週はほとんど音楽に食指は動かず。
クルマは先週、車両登録が済んで車検証のコピーを頂いてきたところ。週初めに任意保険の車両の変更を済ませればあとは納車を待つ、というかディーラーに行くだけとなった。
そんなわけで今週不本意ながら都合1.5日のお休みを頂く予定となっている。
ここまでおよそ3か月。結構気を揉む展開に少々ぐったり。しかしディーラーに寄って自分のクルマを見るたびに、やっぱりニンマリとしてしまう。
仕事は相変わらずの忙しさ。いや忙しいというのとはちょと違うか。抱える案件はそれほどでも何だか面倒な、というかシビアな案件が立て込んでいる状況に疲労困憊?
まあ、ウチの職場で定型通りに進む案件というのはほとんどないのだが、こうも立て続けでは身が持たなくなりつつあり。
そんな今日はR・シュトラウスの音楽を。
音楽で表せないものは無い、と豪語したとかしないとか(笑)というリヒャルト・シュトラウス。流麗華麗な曲想とオーケストレーションを素晴らしいと思う反面、ちょっと苦手にしているウィッチ。カラヤンやショルティ、ケンペやメータなどいくつかディスクを持っているがほとんど聴くことがない。
今日聴いたのはデヴィット・ジンマン/チューリッヒ・トーンハレのBOX。
リヒャルト・シュトラウス=ゴージャスってなイメージがあって、オケの力量を示すのには絶好の曲だけあって、ベルリンやシカゴといったパワー系オケの十八番となっていることが多い。その中でジンマン/チューリッヒは比較的地味な演奏。それだけに等身大というか素顔のリヒャルト・シュトラウスが垣間見える演奏か。録音もそれなりで。
まあ、ぼんやりと聴くには良いのかと思う。
つらつらとリヒャルト・シュトラウスを聴いてきて、ふとマーラーの3番あたりが聴きたくなってアバド/ウィーンのLPにチェンジ。
カートリッジはシュアーのM97xe。レコードプレーヤー純正のシェルに取り付けているもの。やや(音楽の迫力という意味で)物足りないところは感じるが、ハッタリの無い素直な出音ともいえる。音のエッジもそれほど立たずノイズもそれほど拾わないので聴きやすい。
旗艦カートリッジのオルトフォンMC☆20wは音溝を掘り起こすような感じに加え、ややふっくらと聴かせるので盤によってはうるさく感じてしまうこともしばしば。そんな時にこのシュアーは重宝する。
このアバドの3番は80年の録音。
70年代から80年代にかけてシカゴとウィーンを振り分けて1番~7番までセッション録音が進められていた。90年代に入ってシカゴとの1番・2番・5番、6番・7番のうち、1番・5番はベルリンと、2番をウィーンとライヴ録音し、6番・7番はシカゴのままで、97年にベルリンと8番をライヴ録音して全集完成とした。
晩年になってルツェルンの祝祭管と2番を再録音し、3番・4番・6番・7番・9番をベルリンと再録音しているが、もう何が何やら。整理しようと書いてみても何が何やら。大地の歌を録音していないようだがマーラー没後100周年のライヴ映像は残っているみたい。
86年からウィーン国立歌劇場の音楽監督、90年にはベルリンの芸術監督となったことでこのようなことになってしまったのだろう。
アバドの熱心な聴き手ではないウィッチにとっては混乱の極みで現在までフォローしきれていないのが現状。
さて、このウィーンとの3番はいわゆるマーラー的なものは残しつつも洗練された感じか。踏み込みが足りないというよりは、敢えて踏み込まない感じ。クラシックを聴き始めたときはマーラーブームの真っただ中。すでにマゼールは進行していた。で、インバルとベルティーニにシノーポリによる全集が始まった頃。マーラー演奏が客観的・俯瞰的な演奏、冷静なアプローチに移行しつつあった時期。ネオ・マーラー・ルネッサンス(なんかの本に書いてあったような)。
アバドのマーラーはその先頭をぶっちぎりで突っ走るものだった。作曲者と同一化を図るかのような(と言われた)CBSのバーンスタインの全集(実はほとんど聴いていない)の反動のようなところもあるのかと思うし、そのバーンスタインがDGに再録音し、作曲者と見事に一体となるのはもうちょっと先の話だし、実はクーベリック/バイエルンの全集が10年以上も前に遥かその先を走っていたのは内緒の話。